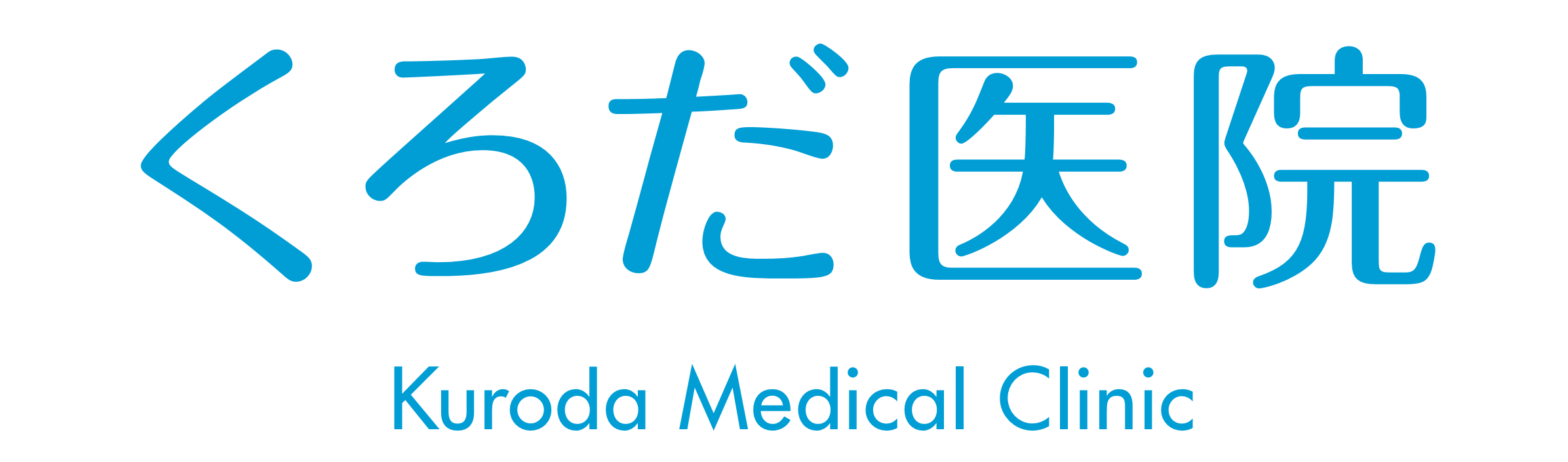Blog黒田院長のブログ
.png)
 2025.05.06
2025.05.06
- 060 オッペンハイマー
今日聴いていた音楽
‘We get Requests’ Oscar Peterson Trio 他このゴールデンウィーク中、私はずっと気になっていたクリストファー・ノーラン監督の「オッペンハイマー」をようやく観ることが出来た。ああそうだ、同時期に話題となった「バービー」はあまり自分の琴線には触れなかった。アメリカじゃお人形遊びするのも色々政治的対立が生じて大変なんじゃのう、くらいなもんか。さて、原爆の父を描いた映画「オッペンハイマー」、ただでさえ我々日本人には非常にセンシティブなテーマであるうえ登場人物も情報量も途轍も無いほど多く、クリストファー・ノーラン監督の十八番というか例によって時系列をごちゃ混ぜにしてくれるので3時間はかなり辛い体験になる。映画は3つのパートに分かれており、1.彼が如何にして原爆開発に携わるようになったのか、2.原爆開発から投下に至る生々しい葛藤とその後に起きた出来事、3.最終的には対立するに至った政府高官の失脚とオッペンハイマーの名誉回復に至る物語 となるが、ノーラン節にしちゃ親切なのは3.のパートがモノクロなんで、素直に違う時系列の話だと理解できる部分か。
1942年にマンハッタン計画が立ち上がった当時、ナチス・ドイツも優秀な物理学者を集めて原爆開発を進めており、原爆の開発競争に敗れることはすなわち敗戦に直結すると考えられていた。戦争指導者達のうち少なからぬ数の人々がじりじりとした焦燥感、危機感を抱いていたのは想像に難くない。劇中でも吐露されるが、ユダヤ系のオッペンハイマーら、ナチスの迫害を逃れてアメリカに渡った科学者たちの「ナチスが原爆を手にしたら我々は根絶やしにされるだろう」との危機感は正当な恐怖であり、開発のモチベーション維持に多大な貢献をしたと推察する。この映画を批判する側の方々が実際に原爆投下された広島や長崎の惨状を描かないのは納得出来ないと言われるのは勿論その通りなのだが、私はあれで良かったのではないかと思っている。例え最先端のVFXを使ってどんな描写をしようが被爆者の体験した地獄は所詮伝えられないからだ。臭いも、全てを焼き尽くした熱も、何もかも。それなら最初から「はだしのゲン」を読め、って話であって。だったら観客の想像力という名の良心に委ねた方が余程被害の凄惨さを伝え得る、きっとそんな作家側の判断が働いたと見えたから。
流石にトリニティ実験から原爆投下後の描写は正視できない中で、私はあの映画を見て一つ確信した事が有る。被爆者の網膜を失明に至るまで焼きつかせたあの強烈な光を避ける防御ゴーグルを着け、自らは安全な避難区域外に居てあの圧倒的な威力を持つ炎を目の当たりにして、魅入られてしまった政府高官の誰かが居たのだ。「神の火」とまで称された恐るべき破壊力、国家予算レベルの大金をかけた兵器を生身の人間に対して行使し、何が起きるのか冷徹な人体実験として試してみたかった我々と同じ人間が居たのだ。その後に想定されていた日本本土上陸作戦、通称オリンピック作戦の犠牲を減らすため、なんて名分じゃ、疑り深い私は騙されないぞ。
戦後ホワイトハウスに呼ばれたオッペンハイマーとハリー・トルーマン大統領の会話場面は実に興味深かった。戦時とその後に続いた冷戦下の政治という酷薄な営みをあの短いシークエンスで表現するには相当な説得力を持ち合わせた俳優で無ければならず、トルーマン大統領役にゲイリー・オールドマンを当てたのは大正解だったと思う。クリストファー・ノーラン監督作品に総じて言える現象だが、適材適所の俳優陣が入魂の演技を繰り広げたこの映画、確かにずっしりとした読後感を残した。ただ、二度と見たくは無い。