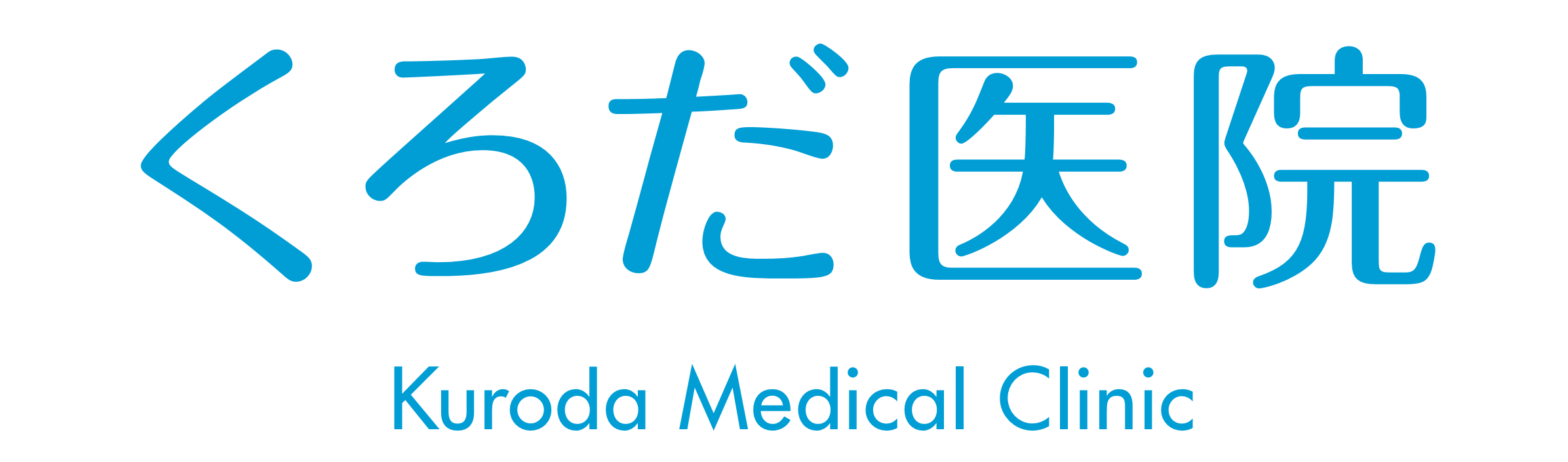Blog黒田院長のブログ
.png)
 2025.05.17
2025.05.17
- 061 プリアンプ考
今日聴いていた音楽
‘Moon Dance’ Ann Sally 他私は1956年製の古いスピーカーで音楽を聴いている。音楽だけじゃ無く、 Netflixでブラックミラーの最新シリーズを見るときも、三遊亭圓生師の「ちきり伊勢屋」を聴くときだってそうだ。夜中に酒を飲みながら古い落語を聴く。歳をとるのも悪い事ばかりじゃ無いと思える、こりゃあ乙なもんです。Altec820Aというそのスピーカーは、現代では時代遅れと言っても良い38cm口径の大きなウーファーが縦に2発入って低音を出し、コンプレッションドライバーユニットが中高域を出す。流石に70歳のスピーカーなので高い音は出せない、そもそも還暦を過ぎた私には超高域なんて出たって聴こえない、、放っとけ。だもんで高域の補助にGauss社製の1502というホーンツイーターを被せてすこぶるご機嫌であった、今までは。
ゴールデンウィークの真っ只中に届いた漆黒のプリアンプが私の平穏を掻き乱してしまった。音量を調節したり種々雑多な入力を切り替えるプリアンプは、やはりオーディオの頭脳と呼んでも差し支え無いだろう。昨今の価格高騰が最早馬鹿らしいレベルに達しているオーディオ機器にあって特に高額な製品が目白押しなのもこのジャンルで、プリアンプとパワーアンプで1000万を超える組み合わせも珍しくなくなってしまった。車じゃないんだよ、走らないのよ? 勿論そういう高額機器、造作は大抵完璧だからニーズに合えば間違いなく幸せになれる。問題は、最大限に頑張って高額アンプを奢っても、じゃあ気持ち良く音楽に没頭出来るかと言えば世の中そんなに甘くないって事である。答えは単純、高いオーディオ機器は「ほぉら金かかってんゾォ」とユーザーに納得させねばならないが、高級でお金のかかった音が必ずしも好きな音とは限らないからだ。試聴して気に入らなきゃ買わなきゃ良いと思うがさにあらず、ちょい聴き程度では分からない違和感が時間と共に増して行き、ついには決裂に至るなんてオーディオでは良く有る話だ。高級オーディオの下取りというのがまた阿漕な世界で、、などという愚痴はさておき、今回試聴したDVAS社製プリアンプ‘Model 3’である。実はこのプリアンプ、まだ市場には出ていない。私が今まで使っていたプリアンプは、マークレビンソンというアメリカのアンプメーカーが出した32Lという機器であるが、後継モデルの52Lが出たときも「新しい方に変えたい」とはまったく思わなかった。32Lは私からすれば真水のようなプリアンプで、ソース機器の素性が良ければそのままに出してくれ、上流の機材が悪ければそのまま出てくる、という性格だと思っているのだが、このDVAS Model3は更に真水の純度を高め、なおかつ現代的な洗練を加えた上で、ここが一番重要なのであるが音楽の楽しさを伝えてくれるのである。私のようなヴィンテージスピーカーを使っている人間にとっても、こんな古い機器を存分に歌わせてくれる稀有な存在なのだ。
前述した通り、お金のかかった高級な音は、必ずしも聴いて楽しい音とはイコールでは無い。勿論一定以上のクオリティは担保されねばならなくて、そこがアンプ開発者の四苦八苦するところなのであろうが、DVASのKさんも開発段階で相当苦労されたと拝察する。どうもヴォリューム調節のパーツがとんでもなく凝っているらしく、スイスのナグラに匹敵するつまみの精密感たるや、あれを酒の肴にカチカチ弄りながら飲めるってものだ。プリアンプを触りながらニタニタしている、世間ではそれを変態と呼ぶのだろう。私が主に聴いている音楽ソースは女性ヴォーカルや歌謡曲、ジャズ、ごく稀にクラシックという感じだが、Model3で聴くElla FitzgeraldやCarmen Mcraeは中央のステージに歌い手がフワッと浮かぶその様が絶妙なのである。故池波正太郎大兄の言葉を借りれば、「そりゃもう、得も言われないもんでございますよ。」ってなもんである。
ゆく河の流れは絶えずして、しかも元の流れにあらず。やはりオーディオも時代につれて進化する。新しい時代の新しいリファレンス、どうやらそんなプリアンプの誕生を目の当たりにしている、私はそんな感覚でいる。